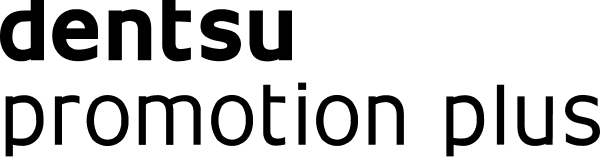2019-08-23
ここにしかない体験を生み出す「ロケーションベースVR」の現在地、最適な活用法
【対談】電通テック×ハシラス――魅力的なVRコンテンツの作り方

認知が拡大し、身近な存在となった「VR」。しかしその世界は現在も、変化し続けています。なぜなら、それほどにVRの持つポテンシャルは高いからです。
その中のひとつ、自宅ではなく、アミューズメント施設や各種商業施設などで楽しむタイプの「ロケーションベースVR」は、VR映像とハードウェア機器を組み合わせ、深い没入体験を提供するものです。
現在、自宅では味わえないその特別な体験価値に、世界が注目。その活用法を模索している段階にあります。
そこで今回、“ビジネスパートナー”である、日本で初めてロケーションVRコンテンツ(VRアトラクション)を制作した株式会社ハシラス 代表取締役社長・安藤晃弘さんと、電通テック UX・コンテンツセンター UXテクノロジー部・白藤誠至が対談。「ロケーションベースVR」の現在地、活用のポイントなどについて意見交換を行いました。
※2022年4月より電通テックから電通プロモーションプラスへ社名変更しました。
その中のひとつ、自宅ではなく、アミューズメント施設や各種商業施設などで楽しむタイプの「ロケーションベースVR」は、VR映像とハードウェア機器を組み合わせ、深い没入体験を提供するものです。
現在、自宅では味わえないその特別な体験価値に、世界が注目。その活用法を模索している段階にあります。
そこで今回、“ビジネスパートナー”である、日本で初めてロケーションVRコンテンツ(VRアトラクション)を制作した株式会社ハシラス 代表取締役社長・安藤晃弘さんと、電通テック UX・コンテンツセンター UXテクノロジー部・白藤誠至が対談。「ロケーションベースVR」の現在地、活用のポイントなどについて意見交換を行いました。
※2022年4月より電通テックから電通プロモーションプラスへ社名変更しました。
拡大し続ける「ロケーションベースVR」市場

左から、株式会社ハシラス 代表取締役社長 安藤晃弘氏、電通テック UX・コンテンツセンター UXテクノロジー部 白藤誠至氏
白藤――安藤さんと初めてお会いしたのは、2015年だったと記憶しています。某商業施設用のVRアトラクションを、ともに制作したことがきっかけでお会いしました。当時からVR業界において、注目の人物だった安藤さん。現在、VRを取り巻く状況をどのように感じていますか?
安藤――これまでも「VRブーム」は存在しました。ですが、今回は違います。一時的なものではなく、このままVRは定着するでしょう。
白藤――たしかに勢いがありますよね、ずっと。2016年にPCベースのヘッドマウントディスプレイ(以下、HMD)が発売されて以降、MRデバイスやスタンドアロン型の発売、五感を刺激するVR連動機器の開発など、家庭への浸透を意識した進化と、「ロケーションベースVR」での活用を意識した進化が同時並行で動いてますよね。
安藤――はい。ですから、同産業において2番目の規模を誇る「ロケーションベースVR」のニーズも、やはり加速し続けている印象です。
白藤――「ロケーションベースVR」の市場は、2018年に、2億ドル(約220億円)にのぼると推計されていました。今後さらに2021年には10億ドル(約1,120億円)まで拡大するともいわれているようですね。
安藤――3年で5倍。それだけの勢いがある市場だと、私自身も肌で感じています。

白藤――その追い風になっている要因として、「ロケーションベースVR」アトラクションに関わる周辺機器の進化も影響しているように思います。少し前まで、何本もコードがあったのに、それが1本に集約されるなど、使い勝手がどんどん向上していますよね。
安藤――はい。画質も向上していますし、没入感はさらに高まっていると思います。
白藤――わからない人からすれば、小さなことのように思えるかもしれませんが、アトラクション中にコードが体に触れたりすると、それだけで現実に引き戻されてしまうじゃないですか。もし数年前に一度、VRアトラクションを体験したことがあるという方がいたら、最新のものにぜひ触れてみてほしい。絶対に驚くはずです。
安藤――でしょうね。ユーザビリティもコンテンツのクオリティも格段に向上していますからね。
白藤――そういった意味では、私たちが一緒に商業アトラクションをリリースした“2016年”というのは、VR元年であり、「ロケーションベースVR元年」ともいえる気がします。
安藤――各社がVRの使い方を模索する中で、スマホで楽しめる簡易のコンテンツ、「ロケーションベースVR」のように施設に行かなければ楽しめないものなどが続々と生まれた年でしたね。
白藤――同じVRコンテンツなのに、自宅で楽しむコンテンツとVRアトラクション(ロケーションベースVR)では、まるで違いますよね。
安藤――はい。ゲームセンターでないと楽しめないゲームが存在するのと同様に、“そこでしか体験できない”価値がVRアトラクションにもあります。
白藤――同時に、その価値を感じてもらえるかどうかが、VRアトラクションの成否を握る鍵になっていますよね。
安藤――はい。映画『レディ・プレイヤー1』では、VRスーツなるものが登場し、仮想世界での感覚を実際に、リアルで感じられるようになっています。しかし、もしそれが本当に実現できたとしても、それを個人で買えるかどうかは別問題ですよね。
白藤――たしかにそうですね。かなり高価なものになるでしょうから。
安藤――その問題を、VRアトラクションなら解決できるわけです。なぜなら、現実や家では絶対にできない体験や、個人では味わえない特別な体験を提供することが、VRアトラクションにとって非常に大切な要素だからです。ですからその価値も、ユーザー視点で考えたときに、「コストパフォーマンスが高いかどうか」という見方が非常に重要になります。
白藤――現在、VRアトラクションのほとんどは有料ですから、選ばれるためにはそうした問題も乗り越える必要がありますよね。
知的財産を活用し、ソフト面で世界をリードする日本
白藤――ちなみに、日本と海外の違いについては、どう感じていますか?
安藤――コンテンツという視点で見ていくと、アメリカはガンアクションが主体です。特にゾンビもの、ロボットものが多いですね。ゾンビが出てきて、それを倒していくものばかり。ですから、コンテンツのバリエーションという意味では、日本は本当に豊富ですよ。
白藤――活用の仕方も違いますよね。日本では、VRアトラクション専門の施設がありますが、アメリカだとアミューズメントパークの一角に、VRアトラクションのコーナーがある印象です。
安藤――そうですね。これはもはや国土と文化の違いなのかなと、私は思っています。HMDを装着して、歩き回る仕掛けを考えても、日本は国土が狭く、土地代も高いため、5メートル四方の面積すら確保するのは難しいといわれますから。
白藤――だからこそ、アイデアでそれをカバーしようと、日本ではバリエーションが生まれたのかもしれませんね。一方で、プレイ時間にも違いがありませんか?日本は比較的10分以下のものが多く、20分以上のアトラクションは少ない気がします。
安藤――コンテンツという視点で見ていくと、アメリカはガンアクションが主体です。特にゾンビもの、ロボットものが多いですね。ゾンビが出てきて、それを倒していくものばかり。ですから、コンテンツのバリエーションという意味では、日本は本当に豊富ですよ。
白藤――活用の仕方も違いますよね。日本では、VRアトラクション専門の施設がありますが、アメリカだとアミューズメントパークの一角に、VRアトラクションのコーナーがある印象です。
安藤――そうですね。これはもはや国土と文化の違いなのかなと、私は思っています。HMDを装着して、歩き回る仕掛けを考えても、日本は国土が狭く、土地代も高いため、5メートル四方の面積すら確保するのは難しいといわれますから。
白藤――だからこそ、アイデアでそれをカバーしようと、日本ではバリエーションが生まれたのかもしれませんね。一方で、プレイ時間にも違いがありませんか?日本は比較的10分以下のものが多く、20分以上のアトラクションは少ない気がします。
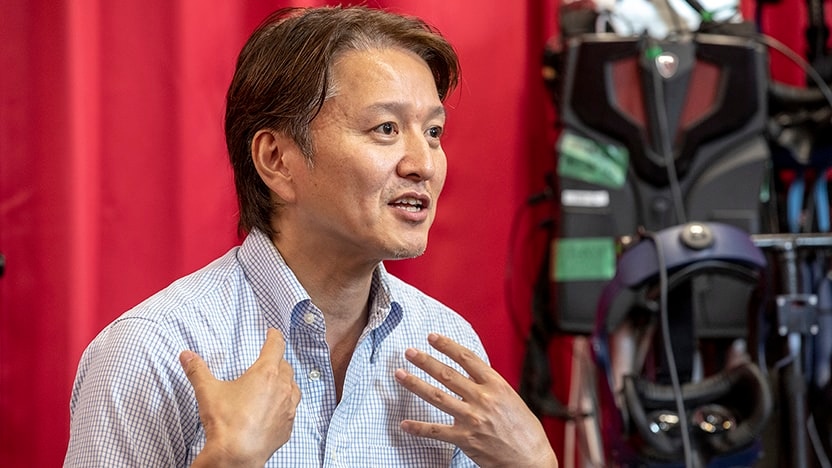
安藤――たしかにアメリカでは、長時間のVRアトラクションも存在します。これもやはり面積の問題で、日本では数を設置できないため、回転率を考えると、どうしても短時間のコンテンツの方が求められる傾向にあります。
白藤――さまざまな制限の中で、モノを進化させていくのは、本当に日本人は得意ですよね。
安藤――はい。おかげさまで、ソフト面の制作技術は、日本は先行しています。ハード面では中国、ついで韓国、台湾が進んでいる印象です。
白藤――となると、アジアが「ロケーションベースVR」の分野を牽引、という未来もあるかもしれませんね。
安藤――すでに韓国でもハシラス製のVRアトラクションが稼働していますし、VRコンテンツの輸出も今後、増えていくかもしれません。何といっても日本には、世界で人気のアニメとマンガがありますから。日本の知的財産を活用すれば、世界中でヒットするVRコンテンツを生み出すことも可能ではないでしょうか。
白藤――そうかもしれません。さきほど体験した『進撃の巨人』のVRアトラクションもすごかったです。キャラクターと一緒に冒険に出掛けている気持ちになれましたし、映像も体験も完成度が高く、とても興奮しました。

VR進撃の巨人 THE HUMAN RACE ~逃走戦線~ ©諫山創/講談社 ©Sony Music Communications Inc.
安藤――ありがとうございます。ただ、VRとの相性という意味では、メジャータイトルである必要はないんです。大切なのは“熱狂的なファン”がいるかどうか。そうでないと、「お金を払ってでも体験したい」とはなりませんから。
いちばん大切なことは、「マイナスをゼロにすること」
白藤――ちなみに、“お金を払ってでも体験したいコンテンツ”を作るためには、どんなことに注意が必要なのでしょうか?
安藤――いちばん大切なことは、マイナスをゼロにすること。没入感を損なう要素は、基本排除することが重要です。たとえば、剣戟のVRアトラクション中、敵に斬られても実際に怪我をすることはありません。ですがその瞬間、私たちは「これがゲームである」ことを再確認し、現実に引き戻されてしまうんです。
白藤――つまり、仮想世界でのリアルと、現実の連動感が重要なんですね。
安藤――はい。ですから、通常のゲームと同じように、見た目や展開のインパクトだけを重視して、VRアトラクションを作ってしまうと「失敗しやすい」ともいえます。
白藤――その点、VR用にハシラスが開発したモーションライドデバイス「キックウェイ」は、素晴らしいですね。VRアトラクションにおいては、身体性をイメージできることが重要だと思います。つまりは、仮想世界なのに、まるでそこにいるような感覚になれる。キックウェイは、それを見事に補完してくれるものだと感じました。
安藤――ありがとうございます。キックウェイは、VRコンテンツの没入感、臨場感を高め、かつVR酔いを低減する効果があります。それでいてコンパクトなのが特徴です。それには、ある秘密があります。実はキックウェイは、前後の水平移動と左右の旋回のみで構成されているんです。これにより、小型化を実現しています。
安藤――いちばん大切なことは、マイナスをゼロにすること。没入感を損なう要素は、基本排除することが重要です。たとえば、剣戟のVRアトラクション中、敵に斬られても実際に怪我をすることはありません。ですがその瞬間、私たちは「これがゲームである」ことを再確認し、現実に引き戻されてしまうんです。
白藤――つまり、仮想世界でのリアルと、現実の連動感が重要なんですね。
安藤――はい。ですから、通常のゲームと同じように、見た目や展開のインパクトだけを重視して、VRアトラクションを作ってしまうと「失敗しやすい」ともいえます。
白藤――その点、VR用にハシラスが開発したモーションライドデバイス「キックウェイ」は、素晴らしいですね。VRアトラクションにおいては、身体性をイメージできることが重要だと思います。つまりは、仮想世界なのに、まるでそこにいるような感覚になれる。キックウェイは、それを見事に補完してくれるものだと感じました。
安藤――ありがとうございます。キックウェイは、VRコンテンツの没入感、臨場感を高め、かつVR酔いを低減する効果があります。それでいてコンパクトなのが特徴です。それには、ある秘密があります。実はキックウェイは、前後の水平移動と左右の旋回のみで構成されているんです。これにより、小型化を実現しています。

ハシラスが開発した「キックウェイ」。狭い空間でも、高い没入感を生み出すことができる
白藤――そうなんですね。体験しているときは、そんな印象はありませんでした。
安藤――はい。実は前傾・後傾の傾斜というのは、視覚的な表現で錯覚させることが可能なんです。ですから、キックウェイではあえて排除しました。また前後左右に動くといっても、実は決して大きく動いているわけではありません。
白藤――それであの臨場感はすごいですね。
安藤――日本におけるVRアトラクションは、定着の兆しを見せると同時に、よりビジネスとしての側面を意識する流れにあります。そのためには、周辺機器も進化し、安価で小型なものが必要だと考え、キックウェイを開発しました。
白藤――VRも現在では広く浸透してきましたから、「VRなら何でもいい」という時代を終え、「本当にいいモノ」が求められるようになってきていますよね。それはつまり、市場が成熟してきた証拠でもあるように思います。
安藤――はい。その流れのひとつとして、コストパフォーマンスも重視される傾向が強まっています。
VRの持つ“没入感”は、教育やプロモーションにも応用できる

白藤――ここまでVRアトラクションとしての「ロケーションベースVR」の話をしてきましたが、現在VRは、教育の分野でも、利用が進んでいるそうですね。
安藤――はい。特にアメリカだと軍事教育に利用されているようです。
白藤――軍事教育というと……?
安藤――たとえば寒冷地や砂漠などでの戦闘訓練は高コストとなります。さらに特別な指導者など、さまざまな準備がいります。ですが、VRを活用すれば、もっと気軽に実施できるわけです。
白藤――なるほど。通常なら高コストになってしまうものを、VRで代用しようという流れがあるんですね。
安藤――まさにそうです。機械の整備など、専門性が高い業務の教育をVRで実施する動きは加速しています。他にも、施設で体験するVRという点では、「VRショールーム」への期待感も高まっています。
白藤――たしかにVRショールームなら、「限りなくリアルに近い体験」を時間や場所を問わず提供できますよね。今はカタログや口コミを見ながら「共感できるか」が購入判断の指標のひとつになっていますが、VRを活用した疑似体験を通じて「五感で共鳴できるか」が指標になったら面白いですね。お客様の目の前に商材をすぐに用意できないものほど、VRショールームは有効だと思います。
安藤――はい。その特性を利用し、今後「ロケーションベースVR」もさらに活用の幅を広げていくのではないでしょうか。
白藤――ちなみに安藤さんは今後、VRや「ロケーションベースVR」を取り巻く環境は、どう変化していくとお考えですか?
安藤――VRの利用が今後さらに拡大していくためには、“便利”であることが重要だと考えています。たとえば、スマートフォンは決して安価ではありませんが、利便性が勝っているからこそ、これだけ普及しているわけです。それと同じことがVRの世界でも起きれば、多くの人がVRを日常生活でも利用するようになるでしょう。
白藤――ARの世界だと、スマートグラスを掛けているだけで自動的に情報が表示される世界が提示されていますよね。それをユーザーが「便利だと思うかどうか」が重要になるのと同じですね。
安藤――はい。ただ、VRの持つ“没入感”をどう活用していくかという視点で考えると、現在の既定路線であるエンタメと教育分野での利用が今後も軸になると思います。白藤さんは、どのようにお考えですか?
白藤――やはり、エンタメが軸になるんじゃないでしょうかね。近年、キャリア各社が5G時代を見据えて、スポーツやライブをVRで配信することに積極的に取り組まれています。離れた場所に居ながら、同一空間で友人と「共体験」できる。すごく便利で理にかなっていますよね。映画館に行く行為や店舗で購入する行為がネットに置き換わってきたように、これまで敢えてその場に行く必要があったテーマパークなんかも、自宅に居ながら仮想空間上で遊べるようになるかもしれませんね。大型テーマパークのようにアトラクションごとにスポンサーがつけば、よりリッチなコンテンツをお客様に提供することも可能なので「VRアトラクション×広告(プロモーション)」という新しい取り組みが、生まれてきてもいい頃ではないかと、個人的には感じています。
安藤――たしかに、まだないですね。
白藤――楽しい体験のあとに続く「リアル体験」は、やはり楽しい思い出になるものです。以前、VR専用CMというものを制作したことがあるんですが、タレントさんがVR上で何度もアイスをオススメしてきて、HMDを外した後に商品をサンプリングするというイベントを実施したところ、お客様の笑顔が絶えなかったんです。同じような文脈でアプローチすれば、企業のブランディングにもつながるのではないでしょうか。
安藤――VRの没入感を利用して、「心に刻む」。面白いですね。
白藤――ありがとうございます。
安藤――ぜひいつか、実現したいですね。
白藤――はい、その際はぜひ、一緒にカタチにしましょう!

体験価値を向上させる“没入感”は、エンゲージメントを高め、企業のブランディングにも寄与するなど、様々な効果を生み出します。現在、VRはエンターテインメント分野での利用が主流ですが、今後、サービスや企業コミュニケーションのあり方もますます「リアルな体験」を重視したものになっていくでしょう。
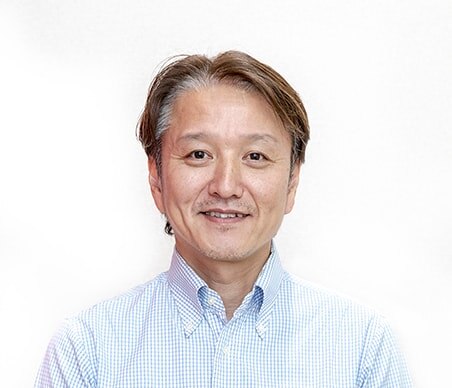
白藤誠至
1997年株式会社電通テック入社。CM制作・劇場映画など映像制作プロデュースを10年経験後、デジタル領域に転向。ブランドサイト、キャンペーンサイト、アプリ、サイネージなどの企画・プロデュースを経験し、2014年より現部署にてテクノロジーを活用したリアルエクスペリエンス領域に従事。
(受賞歴)ACC、Good Design、TIAA、ADFEST、CLIO、CANNES、THE CUP、CODE AWARDなど
(受賞歴)ACC、Good Design、TIAA、ADFEST、CLIO、CANNES、THE CUP、CODE AWARDなど
Written by: BAE編集部
©DENTSU PROMOTION PLUS INC.